本文
FUKUOKA OPEN Lab+[筑豊地区]を開催しました!
本県では、地域共働による社会課題の解決を実現するため、多様な主体の交流の場として、県内各地区で「FUKUOKA OPEN Lab+(ふくおかオープンラボ)」を開催しています。
本研究会は、昨年度開催した「福岡県SDGs推進セミナー&交流会」に、先進事例の研究やワークショップ、学生企画等を豊富に盛り込み、より実践的な内容へとアップデートしたものです。
このたび、筑豊地域で唯一の「SDGs未来都市」である直方市が主催する「のおがたSDGsフェスタ2025」の併設イベントとして、FUKUOKA OPEN Lab+[筑豊地区]を開催しましたので、その模様をご紹介します!
○日時:10月18日(土)13時00分~16時50分
○会場:イオンモール直方 1階 リリーコート(直方市湯野原2-1-1)
○テーマ:「未来へつなぐ ~ひと・まち・自然~」
FUKUOKA OPEN Lab+[筑豊地区]チラシ [PDFファイル/1.65MB]

参加者・登壇者の皆様の集合写真
筑後地区(7月17日)の開催模様はこちらをご覧ください(県ホームページ)
福岡地区(8月7日)の開催模様はこちらをご覧ください(県ホームページ)
プレイベント
開催当日の11時00分から同会場にて、プレイベント「SDGs×ウェルネス講演」を開催しました。
近年の健康志向の高まりや健康経営の広がりを受け、SDGs17のゴールのうち「〔3〕すべての人に健康と福祉を」に特化したコンテンツとして、株式会社ルネサンス 地域健康推進部 次長 丸尾 和久 氏と大林猟師企画 代表 大林 将隆 氏のお二方にご登壇いただきました。
プレイベント登壇者(左から、丸尾氏、大林氏)
丸尾氏からは、企業理念である「生きがい創造」のもと、同社が全国各地で取り組まれてきた地域の健康づくりの取り組みや自治体との連携事例等のご紹介が行われたほか、気軽に取り組めるストレッチを参加者の皆様にもその場で実践していただきました。同社は、「福岡県SDGs登録制度」にもご登録いただいています。

大林氏からは、猟師という立場から、ジビエの可能性や魅力、SDGsへの貢献について分かりやすくお話しいただきました。ジビエの振興は、持続可能な農業を実現するための鳥獣被害対策として重要であるだけでなく、捕獲した鳥獣を廃棄せず美味しくいただくことで、資源の有効活用や新たな産業の創出を通じた農産地域の所得向上にもつながることが期待されています。
お二人のメッセージの共通する点は、「いのち」を大切にすることがSDGs達成やサステナブル社会実現への第一歩であるということです。私たち一人ひとりが、社会とのつながりを持ちながら健康の増進に努めることは「誰一人取り残さない」社会の実現を支える基盤となり、動物の「いのち」をはじめ、様々な資源を有効に活用することは、「〔15〕陸の豊かさも守ろう」など多くのゴールの達成につながっていきます。
オープニング
●主催者挨拶(福岡県 企画・地域振興部 総合政策課 企画監 藤岡 健太郎)
●共催者挨拶(直方市 総合政策部 企画経営課 課長 芦原 昌行)
SDGsクロストーク
SDGsクロストークでは、筑豊地域で「ひと・まち・自然」に関わる活動をする皆さんが、筑豊のポテンシャルを活かし、真の「持続可能な街」にするにはどうしたらよいのかを本音で語り合いました。

ー登壇者のご紹介ー
(左から、宮谷氏、江口氏、安河内氏)
●モデレーター:株式会社ゼロベース 代表取締役 宮谷 直樹 氏
●パネリスト:株式会社NOTE クリエイティブ事業部 マネージャー 江口 葵乃 氏
●パネリスト:一般社団法人嘉麻市観光まちづくり協会 事務局長 安河内 隆 氏

(左から、北野氏、金子氏、鑪野氏)
●パネリスト:大英産業株式会社 経営企画室 係長 北野 真理奈 氏
●パネリスト:学生団体ふーぷ 代表 金子 遙花 氏/副代表 鑪野 結乃彩 氏
クロストーク前半では、各企業・団体からのショートプレゼンを実施しました。各団体の活動概要、活動のきっかけ、これまでの歩み、活動への思い、今後の展望をそれぞれご紹介いただきました。筑豊地域で「ひと・まち・自然」の様々なフィールドを舞台に活躍するパネリストのお話を、参加者の皆様も終始興味深く聞かれていたようです。
クロストーク後半では、SDGsをテーマとしたフリートークを実施しました。その中では、参加者の皆様に「SDGsや社会課題解決に対する率直な思いや、もっとこんな社会になったら良いのに・・・」といったメッセージ等を自由に参加登録フォームに投稿いただき、一部をモデレーターから紹介するなど、双方向のやりとりも行われました。
<実際に参加者の皆様から寄せられたメッセージ(抜粋)>
・全世界で達成しなければならない壮大な目標
・2030年以降、ポストSDGsがどうなるか気になります。
・SDGsにもっと気軽に取り組めるようにしてほしい!
・いっぱいあって難しそう。自分一人の力では何ともならないと思ってしまう。
・非常に重要な取り組み。
・世界が平和であればいいなぁと思います。
SDGsカードゲーム
宮谷 直樹 氏(株式会社ゼロベース)の進行のもと、SDGsカードゲームが行われました。参加者の皆様には、4人1組のチームに分かれて、「Get The Point」というゲームを体験いただきました。ゲームを通して、チームで目標を共有することで資源の枯渇を回避し、持続可能な社会を実現していくというSDGsの本質を体感いただきました。県立直方高校、鞍手高校からたくさんの高校生にご参加いただきました。





ロボット体験会
少子高齢化・人口減少による人手不足問題へのソリューションの1つとして注目されるのが、ロボットの活用です。当日、会場内に体験ブースを設け、九州工業大学大学院生命体工学研究科および北九州市立大学の学生が中心となって結成しているチーム「Hibikino-Musashi@Home」によるロボット体験会を開催しました。

学生の親身なサポートのお陰で、小さなお子さんでも楽しみながらロボットの操作体験をすることができました。

会場の様子

熱心に質問をする高校生

会場にはエコトンも駆けつけました!

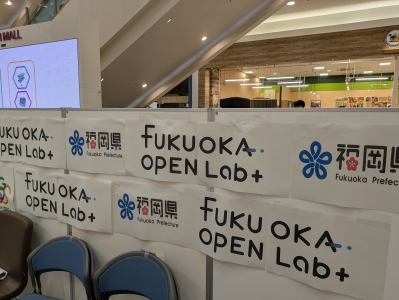
プログラム詳細

今後の開催予定
FUKUOKA OPEN Lab+は、社会課題の解決に取り組む多様な主体に開かれた、研究と交流の場です。県内各地に地域共創の取り組みを広げ、持続可能なまちづくりの実現を目指します。
■FUKUOKA OPEN Lab+ @福岡大学ベンチャー起業論
日 時:令和7年10月28日(火)13時00分~16時10分
会 場:福岡大学 AB01教室
内 容:福岡県SDGs×福岡大学ベンチャー起業論のコラボ授業「学生×企業×行政の共創で社会課題解決へ!」
@福岡大学ベンチャー起業論の開催概要はこちら(県ホームページ)
■FUKUOKA OPEN Lab+[北九州地区]
日 時:令和7年11月8日(土)11時00分~17時00分
会 場:リバーウォーク北九州ミスティックコート、西日本工業大学小倉キャンパス
内 容:北九州サステナブルフェスタ2025実行委員会主催「北九州サステナブルフェスタ2025」併設イベント
※北九州地区の詳細は、確定次第ご案内いたします。
「福岡県SDGs登録制度」に登録してみませんか?
登録申請の通年受付を開始!申請期間を気にせず、いつでも申請できます!
「福岡県SDGs登録制度」は、SDGsに積極的に取り組む県内企業や団体等を県が広く公表し、SDGsへの貢献を「見える化」する制度で、現在の登録事業者数は1,415となっています(令和7年9月末時点)。
登録がお済みでない皆様は、是非ご申請ください。







