

 沖津宮(おきつみや)
沖津宮(おきつみや)北部九州と朝鮮半島を結ぶ海路の中ほどに、その全域が御神体とされる「沖ノ島」はあります。福岡県・宗像市・福津市は、この島をはじめとする「宗像・沖ノ島と関連遺産群」の世界遺産登録を目指しています。沖ノ島では4世紀後半から約500年間、国家の安泰と対外交流の成就を願う国家的祭祀(さいし)が行われてきました。その祭祀遺跡から出土した約8万点の奉献品は全て国宝で、沖ノ島は「海の正倉院」とも称されます。
 奈良三彩小壺
奈良三彩小壺 金製指輪(国宝)
金製指輪(国宝)宗像地域から朝鮮半島へ向かう海路の安全をつかさどるのは宗像三女神(※1)。天照大神(あまてらすおおみかみ)からの神勅(しんちょく)(※2)を受け、今も宗像の地に鎮座しているとされます。
沖ノ島の外周は、岩が切り立つ断崖絶壁。沖津宮(おきつみや)に続く道も畏敬の念を自然に抱かせるように険しいといいます。神宿る島にふさわしく禁忌(※3)も多く、「一木一草一石たりとも島から持ち出してはならない」「島で見聞きしたものは、一切口外してはならない(「不言様(おいわずさま)」という)」など、さまざまな決まり事が現在まで受け継がれています。
※1 宗像三女神…沖津宮(おきつみや)(沖ノ島)の田心姫神(たごりひめのかみ)、中津宮(なかつみや)(大島)の湍津(たぎつ)姫神、辺津宮(へつみや)(九州本土)の市杵島(いちきしま)姫神
※2 神勅(しんちょく)…神の与えた命令、またその文書。ここでは『日本書紀』の天孫降臨の段で天照大神の教えのこと
※3 禁忌(きんき)…してはいけないこと

古代、沖ノ島の祭祀をつかさどり、宗像地域一帯を統治していたとされるのが「宗像氏」です。この地方豪族の墓とされるのが新原(しんばる)・奴山(ぬやま)古墳群。5世紀から6世紀後半にかけて、前方後円墳、円墳、方墳の計41基の古墳が海を臨む場所に築造されており、宗像周辺の海を舞台に活躍し、沖ノ島祭祀を担った一族を象徴するものとして、「宗像・沖ノ島と関連遺産群」の構成資産となっています。。
福津市の「あんずの里運動公園」展望台から見渡せば、大島を真正面に、その先に沖ノ島を抱く海を望みながら今も眠る宗像氏に遠く思いをはせることができます。
■世界遺産登録までの流れ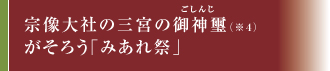
沖ノ島は入島が厳しく制限されており、宗像大社の神職以外は原則上陸できません。そのため、大島の北西岸、沖津宮を遥かに望む場所に「沖津宮遙拝所(ようはいしょ)」が建立され、人々はそこで沖ノ島への祈りを捧げてきました。

宗像の沖合約10キロメートルにある大島には、先述した宗像三女神のうち「湍津姫神」を祀る中津宮があり、「市杵島姫神」を祀る九州本土の辺津宮と向かい合うように鎮座しています。宗像大社秋季大祭「みあれ祭」は、この三宮の「御神璽」が年に一度だけそろうお祭りとして古くから行われてきた海上神事です。
※4 御神璽(ごしんじ)…神社に祀られた神様(御祭神)のしるし
 高宮祭場
高宮祭場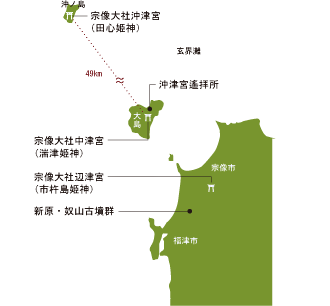
 新原・奴山古墳群
新原・奴山古墳群