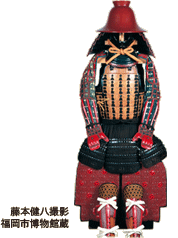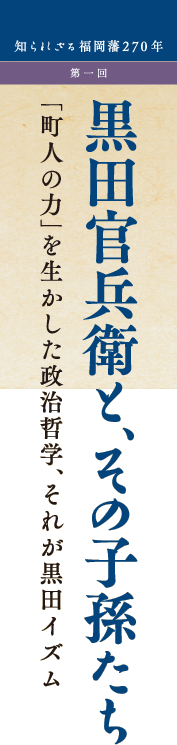

黒田官兵衛(1546年〜1604年)
本名孝高(よしたか)。秀吉のもとで多くの城攻めの指揮を取り、優れた戦略から「稀代の智将」と呼ばれた。息子・長政ともども一時キリスト教に入信するが後に棄教する。隠居後は「如水(じょすい)」と名乗る。この肖像画は、黒田家の菩提寺である福岡の崇福寺に伝来するもの
来年からいよいよ、NHK大河ドラマで、福岡ゆかりの黒田官兵衛を主人公にした
「軍師官兵衛」が始まります。
江戸時代約270年にわたって、福岡の地を安泰に治め、
発展させた黒田家について、その歴史をいま一度振り返ってみましょう。
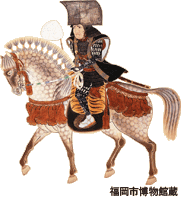
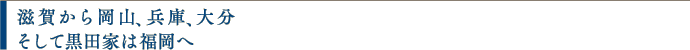
黒田官兵衛の祖先をたどると、琵琶湖の北東、近江国(滋賀県)伊香(いか)郡黒田村にそのルーツがあるといわれています。今も黒田地区自治会館のそばには「黒田氏旧縁之地」の碑が建っています。
16世紀初頭に、足利将軍家の不興を買ってこの地を離れた黒田一族は、次に備前国(岡山県)邑久(おく)郡福岡に居住(この地名が、後にここ福岡の命名につながっています)。さらには播磨(はり ま)国(兵庫県)に移り、大名・小寺政職(こでらまさもと)に重臣として仕えました。官兵衛が生まれたのも、ここ播磨です。
永禄4(1561)年、15歳で父とともに小寺政職に仕え、成人すると父から家老職を引き継ぎます。時流を見る目に秀でていた官兵衛は、織田信長の才能を高く買い、主君にも勧めてその勢力下に付きました。さらには羽柴(のちの豊臣)秀吉の参謀となり、鳥取城の兵糧攻め、備中高松城の水攻め、柴田勝家との賤ケ岳(しずがだけ)の戦い、四国攻め、九州攻めで巧みに作戦を成功させ、秀吉の軍師としてその才能が広く知られるようになります。
秀吉が九州を平定すると、官兵衛もその戦功で豊前国(大分県)6郡を与えられ、中津城主となります。天正17(1589)年に、家督を息子・長政に譲って隠居し、以後は如水と名乗りますが、長政ともども朝鮮出兵に出陣。多くの戦功を挙げました。

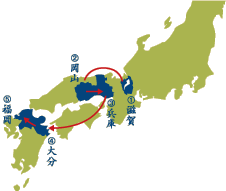
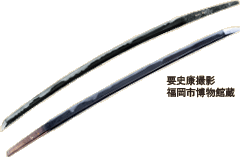
関ヶ原の戦いでは、石田三成との不和があり、長政が徳川家康の養女を正室に迎えていたこともあって、黒田氏は家康側につきます。そしてその勝利に尽力したことが評価されて、家康から筑前国(福岡県)を与えられ、いよいよ入国します。今から413年前、慶長5(1600)年12月のことでした。
秀吉の有能な参謀として、数々の敵を攻略した官兵衛。秀吉は彼を高く買いながらも、一方でその力を恐れていたようです。幕末の館林(たてばやし)藩士・岡谷繁実(おかのやしげざね)が残した「名将言行録」には、こんなエピソードが載っています。 秀吉が家臣に「わしに代わって次に天下を治めるのは誰か」と尋ねたとき、多くが徳川家康や前田利家を挙げたのに対して、秀吉は黒田官兵衛を挙げたとか。「官兵衛がその気になれば、わしが生きている間にも天下を取るだろう」と言ったそうです。それを聞いた官兵衛は秀吉の勘気を危惧し、直ちに剃髪し、如水と称して隠居。長政に家督を譲ったと記されています。